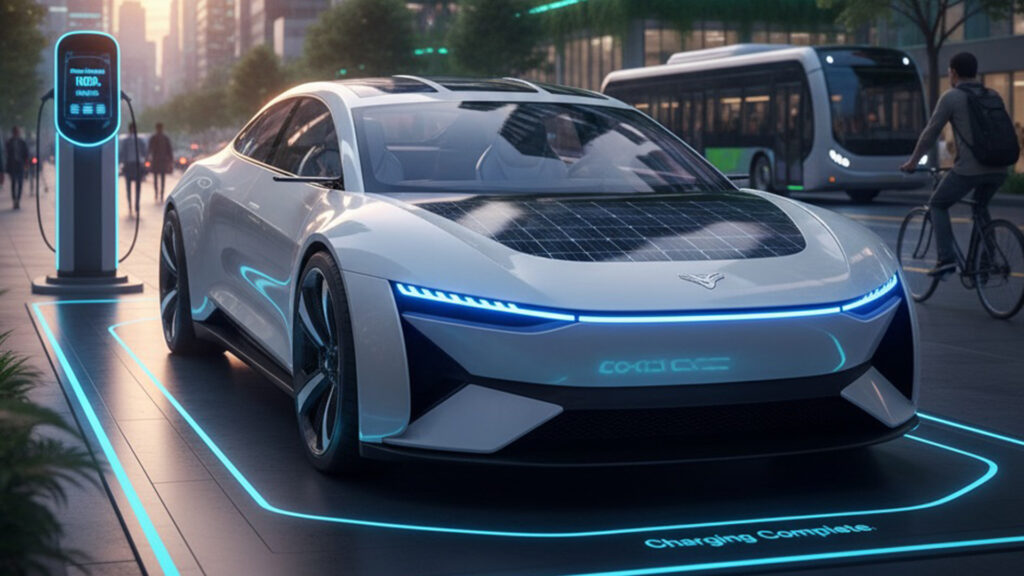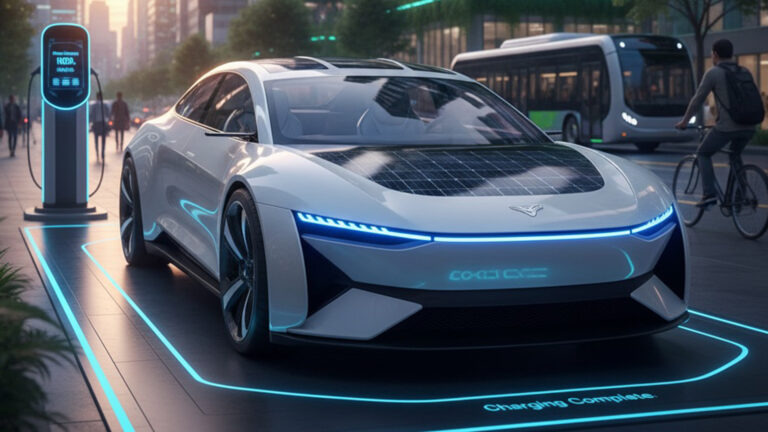近年、政府の発表したグリーン成長戦略等の影響から、多様な電気自動車が日に日に多く普及しています。
ですが、実は電気自動車が生まれたのはガソリン車よりも早く登場していたことをご存じでしょうか?
今回はそんなEVの歴史について解説していきます!
モーターの発明とその実験
電気自動車(EV)の起源については諸説ありますが、EVの特徴は電気モーターで走ることにあり、この発明なくしては始まりません。
様々な背景はありますが、1827年にファラデーの法則に則ったモーターをハンガリーのイェドリク・アーニョシュが発明したといわれています。
オランダのストラチンは一次電池(充電不可の電池)を積んだ電動三輪車の模型を走らせたそうです。
さらに米国のダベンポートも1834年にモーターを発明したといわれています。いずれもモーターで模型の電動車両を動かしたということです。
モーターは小型につくれるので、模型での実証テストが行われた例が多いようです。しかし、一次電池の充電のできない性質もあり、実用化には遠い現実がありました。
鉛蓄電池の誕生
充電可能な二次電池である鉛蓄電池が1859年にフランスのプランテにより発明されています。これが実用化されたのは1880年代に入ってからで、フランスのトルーベがモーターを搭載した三輪自動車を1881年に開催されたパリ電気博覧会に展示しました。これが充電式電池を搭載した最初の電気自動車といえるものでした。
翌82年にはイギリスのアイトンとペリーが0.5馬力のモーターを搭載し、電池のセルを切り替えることで速度を制御し、ライトも装備した電動車両を試作します。これが本格的な電気自動車の起源であるとされています。
ドイツのダイムラーとベンツによる内燃エンジン搭載の三輪自動車の発明が1885年ですから、それより前に電気自動車は誕生しています。
EVの日本上陸
日本に最初に電気自動車が持ち込まれたのは1900(明治33)年で、当時の皇太子(後の大正天皇)のご成婚記念にサンフランシスコの日本人会が献上したものとのことです。米国ウッズ社製の4輪車で、運転席のほか客席が2つありましたから3人乗りといえます。最高速度は29km/hほどであったとされています。
その後も戦争を背景にガソリン統制等が行われたことから、電気自動車の生産の必要性が露わになりました。
しかしながら1950年の朝鮮戦争の勃発により鉛が軍需物資となり、電池の入手は困難となりました。そんな中ガソリンの統制は解除されたので、ガソリン車が優位となり、電気自動車の普及は本格化されませんでした。
環境問題とEV
世界にモータリゼーション(ガソリン車の普及拡大)の動きが高まると、排出ガスの問題が浮き彫りになり、1970年にマスキー法(大気浄化法)が出され、ガソリン車の輸入に制限が掛けられるようになりました。
さらに1973年の石油ショックによる石油高騰の影響も加わり、電気自動車の開発はさらに進みました。
参考:日刊工業新聞社:EVの歴史PDF
グリーン成長戦略の策定
令和3年6月18日に策定されたグリーン成長戦略では、2035年に販売する乗用車の電動化100%を掲げています。政府はV2Hの補助金や普及にも努めており、「電気自動車の蓄電池化」も目指しています。
2050年のカーボンニュートラル化に向け、EV化の動きはますます高まるといえます。
参考:経済産業省:グリーン成長戦略概要
最後に
太陽光発電まるごと安心本舗は株式会社サンエーが運営しております。
再生可能エネルギー事業の他、電気設備工事事業、次世代LED事業など、お客様の生活の質を向上できるよう多岐にわたって事業を展開しています。
「エネルギー問題の解決につながるような取り組みをビジネスの中で実現したい」そんな思いから「化石燃料の奪い合いのない社会」をつくるために、社員全員で最善のご提案をさせていただきます。
お問い合わせは下記より宜しくお願い致します!