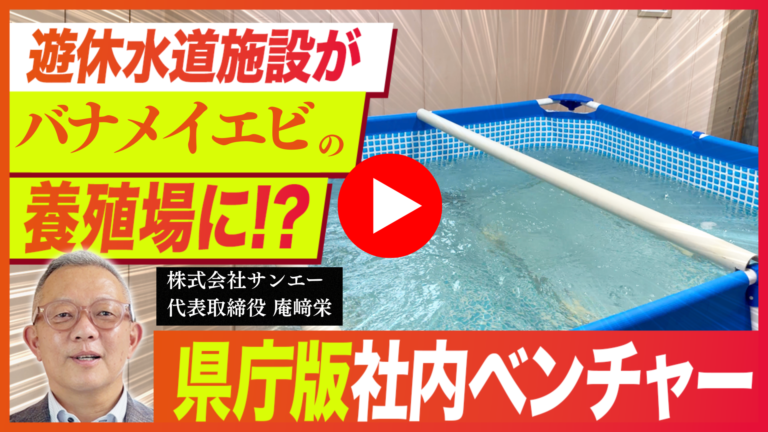路面舗装型太陽光とは
路面舗装型太陽光発電は、道路や歩道、駐車場などの地面に太陽光パネルを埋め込み、新たな「発電する場所」として活用する技術です。土地が限られる日本において、既存のインフラを発電所に変えるこの技術は、再生可能エネルギーの普及を加速させる切り札として期待されています。国土交通省も新技術の導入を推進しており、東亜道路工業がフランスのコラス社と提携して「Wattway」を国内展開するほか、日本道路がエフウエイブ社と共同でトラックの走行にも耐えるパネルを開発するなど、技術開発が活発化しています。
路面舗装型太陽光のメリット
路面舗装型太陽光には、主に以下のようなメリットがあります。
- 未利用スペースの有効活用:広大な道路網や駐車場を新たな発電用地として活用でき、土地確保の問題を解決します。
- エネルギーの地産地消:発電した電力をその場で活用できます。例えば、夜間に道路標識や横断歩道を発光させたり、EV充電ステーションや街灯の電源として利用したりすることが可能です。
- 防災・非常用電源:蓄電池と組み合わせることで、災害による停電時にもスマートフォン充電などの非常用電源として機能し、地域の防災力を高めます。公園の歩道などに設置すれば、電動キックボードなどへの充電スポットとしての活用も期待されています。
路面舗装型太陽光の課題
一方で、普及にはいくつかの課題も存在します。
- 発電効率:太陽光を最も効率よく受けるための傾斜をつけられない水平設置のため、屋根などに設置する一般的な太陽光発電に比べて効率が低くなります。また、通行する車両や歩行者、周辺の建物による影の影響も受けやすくなります。
- コスト:車両の通行に耐える強度や、歩行者の安全を確保する滑りにくさなどが求められるため、特殊なパネルが必要となり、現時点では設置コストが割高です。
- 耐久性とメンテナンス:常に車両や人々に踏まれる過酷な環境にあるため、長期的な耐久性の確保が課題です。また、路面の汚れや損傷に対するメンテナンスの手間やコストが、従来の太陽光発電よりかかる可能性があります。
国内の導入事例と今後の展望
国内では、実用化に向けた実証実験が各地で進んでいます。2017年にセブン-イレブン店舗で導入されたのを皮切りに、近年では東京都が「東京ベイeSGプロジェクト」の一環として2023年に実証を行うなど、自治体主導の取り組みも活発です。また、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)は千葉県浦安市で、歩道と車道に発電パネルを設置し、EVの使用済みバッテリーを蓄電池として活用する実証実験を2023年7月から開始しています。
国土交通省は2025年度から歩道での実証実験を計画するなど、国も技術の実用化を後押ししています。屋根への設置が難しい場所でも導入できるため、ソーラーカーポートや水上設置などと並び、再生可能エネルギーの新たな選択肢として期待されています。コストや耐久性、法律の整備といった課題は残りますが、技術開発と実証実験が進むことで、私たちの足元が未来の発電所になる日が近づいています。